COOP WEB LABO
1パック946ml おきなわの牛乳について教えてもらいました
事業政策支援本部 CRM推進部 上田 千歳
はじまりの前に
2022年の秋、コープ九州の企画編集課という部署でチラシの企画担当だったわたしは
『IRODORIエシカル』という2カ月に1度、偶数月の第一週に入るちらしの実制作を始めようと動き出しました。産直の牛乳を紹介する紙面を作る計画でした。
大好きな子どもの頃から飲んでいる牛乳です(2023年4月1週紙面)

エフコープ、コープさが、ララコープ、コープおおいたのみなさんはこちらの牛乳をお届けしています。
くじゅう・日田地域の原乳を用いています。
牛乳は生協の成り立ちに関わる大切な商品。開発の歴史は古く「組合員の声」で作られた商品です。生協の根っこにあると言っても過言ではありません。
ちなみに生協くまもとと生協コープかごしまは下記紙面になります。かごしまは「コープかごしま牛乳」が誕生したタイミングの紙面になったため、お祝いムードです。
くまもとの原乳は「阿蘇地域」かごしまの原乳は「おおすみ地域」。
そして、おきなわの「コープ牛乳」

!!!!!???
容量が1リットルではない??
そのことにまず???驚きました。
なぜ?
そして原乳は「熊本」!?
ずっと知りたかった
おきなわの牛乳事情について
この牛乳の開発に携わったコープおきなわの砂川花英手さんにお話をうかがいました。
以下、砂川さんのお話しです。

砂川花英手(かえで)さん
2013年コープおきなわに入協。2年間、配達のトラックで地域の宅配を担当、その後宅配の本部や家庭用品の商品部などを経験。2024年現在はバックアップ本部 総合推進室の機関運営マネージャーを務めています。
2016年~2018年、沖縄県の牛の原乳を使ったプライベートブランド(PB)の廃版のタイミングに牛乳や卵の商品担当でした。
なんで今?なんでこのタイミング?
一番先に「コープのプライベートブランドの牛乳を供給できません」とメーカーさんから言われたとき、私が思ったのは「私?そして今?」でした。
沖縄県の酪農家は減っています
県内の酪農家の廃業が続き、沖縄県の原乳の量は減っていました。2015年からおきなわのPBコープ牛乳の数量が限定にせざるを得ない状況に陥りました。
減少した分を、コープ九州の応援によりほかのコープ牛乳で補う、という対応をしていました。
2016年になると、県産の原乳は学校給食を優先することになり、PBの牛乳は特売ができない状況になりました。そして、学校給食もままならないようになり、その年の10月には給食でも加工乳が提供されるまでになっていました。

石垣島の酪農家の牛舎
コープ九州新井知海さんと一緒に
このままでは「コープ牛乳」を供給できなくなる、と頭を抱えていた時、助け船を出してくれたのがコープ九州の日配商品部で牛乳の担当をされていた新井知海さんでした。
新井さんの心強いリードのもと、商品づくりがはじまりました。その中で熊本県の「らくのうマザーズ」が製造くださることが決まり、新しい、コープおきなわのための牛乳づくりを行う事になりました。
熊本県の原乳を用いたものです。
沖縄県の牛乳は946ml、1/4(クォーターガロン)。アメリカの影響を受けたものです。県内の生乳加工業者が作る牛乳はその量で販売されています。
一方ほかの地域で作られるコープ牛乳は1リットル。

左はおきなわでも企画されているコープ九州共通規格の牛乳です。
なじみ深い量で作れないか、らくのうマザーズに相談したところ、新たな製造に挑戦いただけることになりました。パッケージデザインも新しく作らねばなりません。

内田実花さんのブログ「酪農家の一日のスケジュールはこんな感じです。」から
これまで親しんだコープ牛乳の廃版のお知らせを行ったのは2017年12月。
新しい商品の開発を行う一方で廃版のお知らせはどう受け止められるか心配でした。
新しい牛乳の誕生です
2017年3月、らくのうマザーズに製造ラインを見に行き、最終チェックを行ったときは本当にほっとしました。新しい牛乳が誕生です。
同じタイミングで、各センターに新井さんをはじめ、同じくコープ九州の日配商品部田盛誠貴さん、日本生協連の牛乳担当の方が学習会を開催くださり、デビューを盛り上げることができました。

また、「コープおきなわの牛乳はやっぱり一番おいしいよね」という声が組合員から届きました。コープのブランドに対する信頼感があったんだ、と心配していただけに、とても胸に迫った言葉でした。

県内の酪農家の窮状を見て
酪農の状況が厳しいことを知り、県内の酪農家の牧場や牛舎を見に行くこともしました。
そこで初めて「こんなに厳しい中で続けられていたんだ」と知ることになりました。
沖縄は気温も高く、牛(特にホルスタイン種)は高温に弱い生き物です。また、必要な広い土地がふんだんにあるわけではありません。
酪農家に「沖縄で牛乳をするのはむずかしいのよ」と言われました。

平成10年度に160戸あった県内の酪農家は令和4年度に64戸になっています。厳しい産業です。
酪農家さんとお会いすることで、生き物と向き合う、大変なお仕事である生産者さんの現状を知りました。でも、私たちの食卓は、生産者さんなしでは成り立ちません。牛も、生産者さんである酪農家さんも、生き生きと過ごせるような持続可能な酪農は可能なのか?いろいろな可能性を探しながら、模索した数年間でした。結局、具体的な支援にはつながらなかったのですが…「なにか今の自分にできることはないかな」と、牛乳を美味しそうに飲む息子を見ると考えてしまいます。いつまでも、地元産の牛乳が飲めるような環境であってほしいと感じます。

応援のカタチを探したい
当時新しいコープ牛乳を飲んでいただくようにチャートを作成するなど工夫しました。
「くまもとの牛乳もおいしいね」という声もいただいています。一人でも多くの方に生産者さんの現状を知っていただき、みんなで応援できるよう、生協ならではの応援のカタチがみつかればいいなと思っています。

さいごに
酪農家の状況は、沖縄県に限った話ではありません。飼料はもとより、原油価格の高騰など、生産者を取り巻く状況は厳しいものです。
今回の記事が利用する側の皆さんにとって、生産者に思いを寄せるきっかけになればと思います。
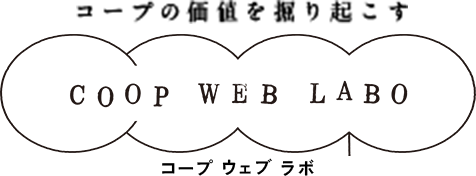












生協にはまるきっかけが生協の牛乳でした。とにかく、2人の息子達が大好きだったのです。27歳と25歳になった今でも毎日飲んでいるみたいです。
ゆきりんさん
コメントありがとうございます。
子どもの頃に好きだったものには思い入れがありますよね。
お子さんたちの成長に生協の牛乳が関われたこと
誇らしいです。ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします!