COOP WEB LABO
その1:コープおきなわ検査センター訪問報告
品質管理室室長宮平さんに学ぶ①
エフコープ 商品検査センター 宮田 有規
私は、エフコープ商品検査センターで微生物検査を担当しています。日頃、エフコープ、ララコープの店舗点検を担当しています。
今回は生活協同組合コープおきなわ品質管理室に訪問し、品質管理室室長 宮平さんの下、店舗点検、微生物検査等の品質管理業務について、実際の通常業務に同行して学んだ。
商品セットセンターでは、おきなわの守り神であるシーサーに出迎えられた。品質管理室は、商品セットセンターの2階に位置し、事務所と準備室、検査室という間取りになっている。

朝礼を終えたのち、宮平さん、パートナーの宮城望さんとコープ山内へ向かった。

1日目 店舗パトロール・店舗点検・手洗い学習会
スケジュール
10:00~ コープ山内 店舗パトロール
11:30~ 手洗い学習会
13:00~ 店舗インストア点検(生鮮4部門+ハートランドベーカリー)
コープおきなわは全部で9店舗あり、山内店は4号店である。到着後、まずは水道の残留塩素を測定した。品質管理室では、試薬を使用して月に1回タンクから1番距離が遠いところ(山内店では2階のホール)を測定した。日常的には店舗で 色、濁り、臭い、味を測定してもらい記録をしているとのこと。

店舗パトロール
残留塩素の測定後、まずは店舗パトロールを行った。店舗パトロールとは、商品管理と表示管理の点検のことで、農産、畜産、水産、惣菜、日配等のほとんどの商品について表示点検を行った。

農産は、名称と産地が合っているか、特別栽培農産物はガイドラインの表示があるか、有機農産物は有機JASマークが付いているか、輸入かんきつ類は食品添加物表示をしているか農薬の表示があるか、野菜の産地をJA〇〇と混同せずに表示しているかを確認する。
また、有機農産物は、店舗で加工(カット)したものについては、値札に「有機○○」と明記していないかを確認した。(※指定の加工場で加工したものであれば、「有機○○」と明記できる。例えば「大根を半分でください」と言われることがあり、対応後残った半分の大根は有機農産物であっても、通常の大根として販売する。大根の段ボールの有機JASマークを近接に掲示することは出来る)

畜産、水産、惣菜、日配は、期限およびアレルギー表示が間違っていないかを確認した。を確認した。西京焼きのような店内加工品は、値札シールとは別に、味付けに使用したタレの原材料等の表示があるかなどの確認を行った。
値引きシールは、原材料等の表示が隠れるように貼られていないか注意してみるように指導いただいた。サイズが小さい商品については、表に記載された商品名は正規の名称ではないため、そこに貼り、裏面の一括表示や組合員が必要とする表示が隠れないように貼るようスタッフに指導しているとのこと。

宮田の感想
今回初めて表示の点検方法について指導していただき、たくさんのルールがあることを改めて知った。アレルギーを持っている方など、人によっては命に関わるほど重要なものであるため、適切に表示されているか確認することは非常に重要である。私も点検時に確認してみようと思う。
手洗い学習会

品質管理室が行う手洗い学習会は、座学ではなく、手についた汚れに見立てて専用ローションを塗り、手洗い後ブラックライトの下に手をかざし、洗い残しの有無を確認する簡易的な学習会である。
手洗い学習会を行うタイミングは年2回(5月と11月)で、手洗い選手権を行う前の月に実施する。
そこで自分の手洗いのクセや洗い残し箇所を確認し、翌月の手洗い選手権に活かす、という目的がある。この学習会は、手洗い選手権の結果が良くなかったことをきっかけに始まり、現在まで継続して行っている。

当日は、開始前に各部門を周りスタッフに声掛けを行う。そこから1時間程度、スタッフが確実に通る事務所前に手洗いチェッカーとブラックライトを設置し、空き時間に手洗いを行ってもらう。時間はスタッフが出勤、退勤をする昼頃に行う。参加者については、それぞれの手洗いレベル(上級、中級、初級、マイスター)を確認しながら、チェックを付けて出席を取る。
この学習会は、手洗いの結果を確認する他に、顔を覚えてもらったり、店舗スタッフの顔と名前を覚え、会話をすることでコミュニケーションを取り、関係づくりをすることも大きな目的である。
手洗い学習会にはほぼ全員のスタッフが参加していた。宮平さん、宮城さんと和気あいあいと話しながら楽しくやっており、うまく洗えていなかった方には、洗えていない箇所、洗い方などを指導し、もう一度手を洗いに行っていた。

みなさんやる前は、あまり乗り気ではなかったが、実際にやってみると熱心に取り組んでおり、マイスターの方については、マイスターの名の通り完璧に手洗いが行えていた。一番驚いたのは、宮平さんがスタッフ全員の名前を覚えており、人によっては下の名前まで覚えていたことだ。翌月の手洗い選手権に向けての学習の意味もあるが、本当にコミュニケーションを大事にされていることがわかった。
宮田の感想
組合員や学童のお子さんには手洗いチェッカーを使用した学習会(出前実験)を行っていたが、店舗スタッフを対象にやってみるのもいいなと思った。また、そこで一人ひとりとコミュニケーションを取れるのもいいなと思った。エフコープの点検では、目線を変えるために点検に行く人を毎回変えているため、なかなか顔と名前を覚えることは難しいが、名前で呼ぶこと、コミュニケーションを取ることが重要であると改めて感じた。
店舗インストア点検

作業場の点検は、水産、惣菜、畜産、農産の生鮮4部門とハートランドベーカリー(株式会社ハートランドおきなわ(就労継続支援A型事業所のスタッフ)の計5部門をそれぞれ30分程度行う。
手洗い学習会と一緒に実施し、1ヶ月の間に9店舗すべて行くことになっている。その理由として、「現在のコープおきなわの店舗の衛生状態を把握し、翌月のまもる君会議※で報告する」「お盆、年末年始の大きな行事の前に点検を行うことで、衛生管理への気を引き締めてもらい、大きな事故を未然に防ぐ」などがある。

事前に副店長に点検に行くことを連絡し、当日は現場の衛生管理の責任者である副店長に同行してもらい、都度、聞き取り、報告をする。
点検時の装備は、点検用の上着、キャップ、マスク、コックシューズで棒(グレーチング、グリストラップを開ける用のフック付きの棒(50センチくらい)と結果を入力する用のスマホおよびタブレット。
点検の流れは、「店舗インストア点検表」の30個の項目(部門によって一部内容が異なる)に沿って点検を行う目視点検と、帳票類の確認。写真を撮影、コメントもその場で入力する。点検終了後に報告書を提出し、1週間を目安に改善報告書を作成してもらう。宮平さん曰く、点検はスピード感が重要であり、点検時の熱が冷めないうちに、報告書を提出し、改善してもらうことを大切にしている。

点検については、作業場自体はやはり整理整頓されており、きれいな印象であった。シールはきれいに収納されており、壁にも最低限の掲示しかなかった。しかし、指摘事項については、持ち込み禁止物(クリップ、ホチキス)や段ボールの二次利用、原材料の保管温度間違いなどエフコープの店舗店点検と同じような指摘であった。


宮田の感想
点検する部門数が他の生協とは異なったが、点検方法、指摘箇所等は特に変わらなかった。作業場の整理整頓はしっかりとされており、無駄な掲示物やものがなくすっきりとした印象であった。また、基礎的なレベルは高いので指摘箇所についても細かく指摘していた。
1日目の振り返り 宮平さんから教わったこと(一部抜粋)
店舗点検について、初めは店舗に行くと嫌な顔をされていたらしい。それは、「何のために点検を行っているのか(→組合員のため)」が伝わっていないことが原因でもあるため、そこをしっかりと伝えるようにした。とのこと。
報告書の上にも何のために行っているのかを書いて伝えている。
また、前述したとおり、店舗スタッフとのコミュニケーションを大事にしており、パトロール(表示点検)時も常にスタッフに話しかけるようにしており、インストア点検時も一方的な指導ではなく、会話の中で改善方法を一緒に考えるようにしていた。もしも間違っていれば、そこは宮平さんから助言するようにしており、自分で考えてもらうことも大切にしている。

そのおかげもあり、フードスタンプで結果が悪かったときは、夜間の清掃スタッフと現場スタッフがコミュニケーションを取りながら話し合い、分からないことがあればすぐにメールで宮平さんに聞くなどし、改善に至ったという事例もあったそう。そして、まもる君会議で良くなったことの事例共有、他店舗がそれを真似しどんどんレベルアップしている。
宮平さんに「店舗点検の指摘数が多い時どうしてる?」と聞かれ、「報告書に書ききれない場合は、優先順位をつけて、取捨選択しています」と答えると、「それはだめだね」と言われた。確かに指摘の数が多すぎると、店舗側がどうかなと考えてしまうことがある。しかし、改善できるできないを判断するのは店舗側で、こちらは悪いと思うことはすべて伝えるべき。指摘が多いかなと思うのではなく、もっとよくなったらいいな、ここが改善できたら、さらに店舗の衛生レベルがあがるな、という期待を込めて指摘をするべきと教えていただいた。

コープおきなわ 品質管理室訪問報告は次に続きます。
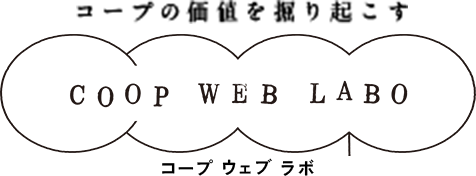



5月に組合員さんと学習会をするのでとても良い参考になりました。
ありがとうございます🙇
ふみふみさん
コメントありがとうございます。
コープおきなわさんを訪問した際に印象に残ったことを書かせていただきました。
私自身とても勉強になったので、少しでもみなさんに共有できれば幸いです。