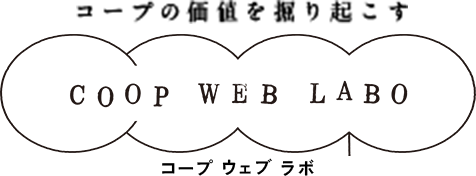COOP WEB LABO
高原から届くレタス 産地は川上村です
CRM推進部 上田 千歳
長野県、群馬県の産地の点検に同行した2025年5月。最後に訪問したのが、標高の高い高原、長野県川上村、日本一の出荷量を誇るレタス産地です。
目的地のJAまで、先に何かあるのか不安になる山の中を抜ける道中。
たどり着いたのがJA川上そ菜。美しい水が流れる緑の中にたたずむJAです。
川上村は高原で寒暖差が大きく、レタス栽培に適している地です。

生産指導の担当である中嶋定利さんから伺いました

今年の作況について
標高の低いところから生産が始まるレタス。天候もまずまずで順調にスタートをきれているそうです。
これから収穫までで心配なことは何ですか?に「大雨と高湿度です。ゲリラ豪雨が起こると病気が出たり、と大変なことばかり」とのこと。7、8月に降る雹も大打撃になるそうですが、この数年は降っていないためそちらは大丈夫かな?と教えていただきました。
レタス生産者のみなさんについて
現在、中心で生産を行っている生産者の皆さんは川上村のレタス栽培60年の歴史の中での2代目や3代目のみなさん。38軒のうち14軒の農家が生協向けに出荷くださっています。農家の後継者問題についてはもれなく川上村も直面しており、高齢化と新規就農のなさで軒数は減少しているそうです。中心的に頑張られている農家さんは40代ですが作業負荷がかかる玉レタスからサニーリーフづくりに切り替える方もいらっしゃるそうです。
ほかの作物と同様に海外からの研修生が作業には欠かせない存在です。
種、苗、土や肥料など、資材の値上がりは大変ではないですか?とお聞きしたところ、肥料と農薬の値上がりが非常に大きく、レタス栽培に必須のマルチ※も値上がりした上に、廃棄にも費用が掛かる、とのこと。お聞きしていると申し訳ない気持ちになる話ばかりでした。
施設を見せていただきました。

出荷のために一度JAに集荷されるレタスたち。シーズン中は朝5時から11時まで受け入れを行うそうです。
という事は、収穫は夜中スタートです。

コンテナに入れるなどして、農家から届いたレタスは左奥に見える「真空冷蔵庫」で予冷されます。20分かけて急速に冷やすことで、この後の鮮度が違ってきます。
予冷後、冷蔵庫で出荷を待ちます。
「集荷された2~3時間後くらいには出て行っているかな」と中嶋さん
圃場に向かう途中質問しました

「春先に苗を植えるレタス、播種(種まき)は誰がするんですか?」
とお聞きしたところ
自分で播種する農家と業者に依頼する農家がある、とのこと。冬場には冷えるこの地方で、発芽するための温度を保つためには暖房を入れないと無理だとお聞きし「暖房費・・・」とキャベツの播種の際も思ったことを同じように思いました。
(ちなみに嬬恋のキャベツ 石油の暖房と薪のストーブの農家さんがいます)
4月になると、ほとんどの農家が自宅で播種を行うそうです。6月中旬から下旬にかけ24cm~25cm間隔で苗が植えられていきます。
一面レタス畑!
どこまでもレタス畑。

レタスは温度や水分の変化を嫌うため、マルチ※栽培を行います。植えられる前の畑はギンギンに輝いています。
それがレタスが成長すると一面グリーンの畑に変わるのです。
マルチ…畑の畝を覆うことで、雑草の抑制、土壌の水分保持、地温の安定化、肥料の流出防止などの効果をもたらす農業技術。
お会いした生産者さんにお聞きしました

小林嵩久さん
レタスを作り始めて10年目という小林さん。植え付け前の畑をご家族やスタッフのみなさんと整えているところに突撃しました。
レタスを生産する理由や楽しさについてお聞きしたところ
「たまたまうちがレタス農家だったから。。。」としばし言葉を失われました。リアルです。
「大変なことはすぐ言えます。うまくいかないことも多いです。あ、でも全国のみなさんが食べてくださるのが嬉しいって言えばいいかな」と思いやり回答をいただきました。

お話の後方でトラクターの通り道を作り、マルチの上部を苗を植え付けやすいように平らにする作業をされているご家族にご挨拶をしたところ、元気に手を振ってくださいました。
突然な上、手を止めていただきありがとうございました。
車で移動中、もうおひと方、生協向けのレタスを生産者にお聞きしました。

レタス農家に生まれた高橋さんは大学時代は宮崎県に出られていたそうです。一緒に作業されていたお母さまが「九州はいいところよね」と優しく声をかけてくださいました。
「大変なことと楽しいこと半分半分です!」
「20代の生産者もまだ3人います!」と教えていただきました。
リーフレタスの生産に切り替えられている、とのこと。高橋さんも生産される「サニーレタス」は6月から企画が始まっています。
山々に縁どられた一面に広がる(ぎんぎん)の畑

収穫の2週間前に結球をはじめるため、そのタイミングの景色がいいですよ!と、中島さん。
JA川上そ菜の中嶋さんも、生産者のみなさんも、飾らないお人柄で川上について、生産の今について教えてくださいました。
土地が持つ力を最大に活かして育まれたレタスです。「7月から9月の間にしっかり食べてください!」に応えて、ぜひこれからも食べて生産現場を応援していきましょう!